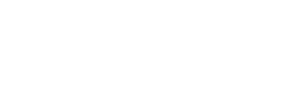小松菜の行き場がない…大量廃棄を止めるために企業ができる選択とは?
小松菜は安定供給の裏で、フードロスの代表格に
小松菜は、1年を通して安定して出荷される野菜のひとつ。
スーパーや八百屋でも常に棚に並び、
家庭でも飲食店でも使いやすい万能食材です。
クセがなく、加熱も簡単で、
健康志向の高まりもあって消費量は安定しています。
しかしその“安定性”が裏目に出ている側面もあるのです。
実は小松菜は、野菜の中でも
特にフードロスが起こりやすい品目だと言われています。
特に農業法人や契約農家、
流通企業の間では、
こんな課題が常にくすぶっています。
- 収穫のタイミングが集中し、在庫が一気にダブつく
- 少しの傷みや変色で返品対象になり、出荷できなくなる
- 市場価格が下がりすぎて、出荷しても赤字になることがある
その結果、「まだ食べられるけれど、小松菜を畑に戻す」
「収穫しても採算が取れず廃棄せざるを得ない」などの声が、
現場ではよく聞かれます。
「売れないけど、捨てたくない」企業のジレンマ
小松菜は見た目が少しでも悪くなると敬遠されやすく、
特に葉物は傷みが早いという特徴もあります。
また、成長が早いため、
少し収穫のタイミングがズレただけで
大きさが不揃いになったり、
硬くなったりして“規格外”扱いされることも。
流通業者や小売企業からすると、
小松菜は“量が読みにくく、
捌きにくい野菜”でもあります。
さらに、天候に恵まれた年などには、
想定外の豊作になり、
一時的に大量の小松菜が市場に流れ込むこともあります。
しかし、販路には限界があります。
売り切れなかった分はすぐに劣化してしまうため、
売れ残った小松菜は最終的に廃棄される運命にあるのです。
「せっかく育てたのに、捨てるのは心苦しい」
「人手もコストもかけて収穫したのに、
売れずに終わるのは虚しい」
そう感じている企業も多いのではないでしょうか。
小松菜を無駄にしない現実的な選択肢:「ベジブル」に出すという手段
そんなジレンマを抱える企業にとって、
“ベジブルに小松菜を提供する”という方法は、
非常に現実的かつ効果的な選択肢です。
ベジブルは、まだ食べられるのに市場から
はじかれてしまった食品を引き取り、
必要としている人たちや
新たな販路に届ける仕組みを持っています。
ベジブルが対象としている小松菜の一例:
- 見た目に少しキズがある
- サイズが不揃い
- 収穫量が多すぎて流通しきれない分
- 店頭で販売できなかった“賞味期限内”の在庫
これまで「捨てるしかない」と思っていた小松菜も、
ベジブルに出すことで、
誰かの食卓に届く“価値ある商品”として
再び命を吹き込まれるのです。
企業にとってのベジブルのメリットとは?
1. 廃棄コストの削減につながる
食品を捨てるにもお金がかかります。
処分費用、人件費、物流費などを含めると、
廃棄するだけで数十万円規模のコストが発生することも。
ベジブルに提供することで、社会的意義も生まれます。
2. CSR活動やSDGsの実績として活かせる
「まだ使える野菜を、無駄にせず役立てた」
その実績は、企業の社会的責任(CSR)や環境への取り組みとして、
社内外に発信することが可能です。
取引先や消費者からの評価が高まるだけでなく、
社内のブランド意識の醸成にも貢献します。
小松菜の未来を変えるのは、あなたの会社かもしれない
「小松菜がありすぎて困っている」
「もう出荷しても意味がない」
「このまま畑に戻すしかない…」
そんなときこそ、ベジブルに声をかけてみてください。
難しいことはありません。
余剰分・規格外・売れ残りの小松菜に対して、柔軟な対応が可能です。
“捨てる”以外の選択肢を、いま企業が持てること。
それは、環境にも、社会にも、
そして会社自身にも良い影響をもたらすはずです。
小松菜のフードロス、今日から減らせます
まだ食べられるのに、行き場を失っている小松菜が、日本中にあります。
その小松菜の“命”をつなぐ方法として、ベジブルという存在があります。
企業として何かしたい、でも大きなことはできない。
そう感じている企業こそ、“小松菜を無駄にしない”というシンプルな取り組みから始めてみませんか?
まずは一度、ベジブルにご相談ください。
“捨てない選択”が、企業の未来を変えていきます。