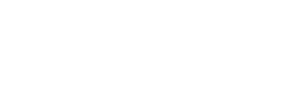「もったいないを、ありがとうへ。」を事業の核に――私たちはゼブラ企業として持続可能な未来を築きます
私たちはこれまで、「訳あり」「余剰」「規格外」といった理由で行き場を失う食材と向き合い続けてきました。
それは単なる安売りや仕入れではなく、地域の困りごとを解決するための挑戦でした。
今、改めてここに宣言します。
私たちは、利益と社会性を両立する「ゼブラ企業」であることを選びます。
私たちの事業の中心にあるのは、「もったいないを、ありがとうへ。」という理念です。
この言葉の奥には、生産の現場や流通の現場で毎日のように積み上がる廃棄と、目の前の生活に困る人々の存在が重なっています。
「まだ食べられるのに、捨てられてしまう野菜を、必要な人の手に届ける」。
シンプルですが、それを仕組みとして成立させることは容易ではありません。
■ 余剰・規格外を価値に変える仕組み
たとえば近年、企業様の物流や在庫管理の都合により、
- じゃがいも24トン
- 大根10トン
という膨大な量の余剰が発生しました。
もしもこうした在庫を引き取る事業者がいなければ、その多くは廃棄処分されていたはずです。
しかし私たちは、農産物の価値を正当に評価し、生活者の目線で「まだ食べたい人がいる」と信じ、買取と再流通に踏み切りました。
こうした取り組みは、農業の生産現場だけでなく、加工・流通・小売を含めたサプライチェーン全体の無駄を減らす動きの一端を担っています。
この挑戦は、食品ロス削減の目標だけでなく、地域経済の循環にもつながっています。
■ 支援の先にある「共生の形」
訳あり野菜や余剰在庫の再流通は、単なる安さやお得さだけで語れるものではありません。
そこには、支援が必要な人や場所があります。
私たちはこれまで、
- 子ども食堂
- 保育所・福祉施設
- 地域イベント
といった多様な場面で、野菜や果物を提供してきました。
また、大手自動車メーカーの社内イベントでの活用など、企業の枠を超えた協働も進めています。
単なる販売ではなく、「共に食を楽しむ体験」をつくることが、野菜の価値を伝える手段だと考えています。
野菜は、人をつなぐ媒介でもあります。
生産者、企業、消費者、地域の子どもたち。
そのすべてが「いただきます」の言葉で結ばれる、そんな関係をこれからも増やしていきたいと願っています。
■ なぜゼブラ企業を選ぶのか
ユニコーン企業のように短期的な成長や独占を目指すのではなく、
白(社会性)と黒(収益性)がシマウマの縞のように交わり合う――
これが、ゼブラ企業の本質です。
私たちは、
- 誰かの困りごとを事業の起点にすること
- 寄付や一過性の支援ではなく、持続可能なビジネスモデルとして成立させること
- 成長を急がず、地域と共に歩むこと
これらを事業の軸に据えています。
この姿勢は、派手な拡大や注目を集めるものではないかもしれません。
けれども、「もったいないを、ありがとうへ。」を一つずつ積み重ねることが、地域に根ざす企業としての誇りです。
■ 代表メッセージ(堀内 塁)
どれだけ形がいびつでも、どれだけ余っていても、野菜には命があります。
現場を見て、触れて、味わってきたからこそ、この当たり前を忘れたくありません。
規格や数字の先にいる、生産者の想いと消費者の暮らしをつなぎたい。
私たちは、ゼブラ企業として、社会性と経済性の両立を追い求め、未来の当たり前を育てていきます。
■ 取材・協業のお問い合わせ
私たちの活動にご関心をお持ちの企業・メディア・団体の皆様は、以下よりお気軽にご連絡ください。